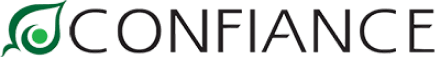スキンケア成分選びの基礎知識

スキンケアの成分選びで迷っていませんか?テクスチャー設計や肌への優しさを重視した選び方を、プロの視点で解説。
「話題の成分を使ったのに売れなかった」「ナチュラル成分を選んだつもりが肌荒れが起きた」――
スキンケア商品を企画・販売する中で、このような経験をお持ちではないでしょうか?
スキンケア開発において、成分の“効果”や“話題性”だけで判断するのは危険です。特にOEMや自社開発を目指す事業者にとって、テクスチャー(使用感)やターゲット層との相性を考慮した成分設計が、製品の評価とリピートにつながるカギになります。
本記事では、プロのOEM現場で実際に実践されている成分選定の考え方や、原料トレンド、誤解されやすい表示について、わかりやすく解説していきます。
この記事でわかること
スキンケア商品を開発・選定する際に、成分選びで重視すべきポイントや、誤解しやすい表示内容の正しい理解が得られる。
この記事のポイント
・使用感とテクスチャー設計がリピート率に大きく関わる理由
・天然由来成分とケミカル成分のバランス設計の考え方
・成分表示にまつわるよくある誤解と正しい捉え方
使用感・テクスチャー設計がリピートを左右する理由
どれだけ話題性のある成分を使っていても、使い心地が悪ければリピートにはつながりません。
実際、あるOEM事業者では、当初SNSで話題になっていた新成分を導入した商品を開発しましたが、使用感の重たさが理由でリピート率が低下したという事例がありました。
こうした経験から、同社では処方バランスの調整を重視し、ターゲット層や季節性に合わせたテクスチャー設計を徹底。例えば、乾燥が気になる40代以上の女性向け商品では、こっくりとした保湿力重視の処方を、若年層向けの夏用化粧水ではさっぱりとした冷感系の使用感を採用するなど、使用場面ごとに設計を変えています。
とはいえ「テクスチャー重視」といっても、やみくもに感触を良くする成分を入れればよいわけではありません。次章では、そのバランスの取り方について見ていきましょう。
ケミカル vs 天然成分 ― 使用感と安全性のバランス
スキンケア業界では、「天然成分=肌にやさしい」「ケミカル=悪」という図式が流布されていますが、実際にはそう単純ではありません。
取材企業では、「安易にテクスチャーを良くするためにケミカル成分に頼ることはしない」という方針を徹底しています。試作を繰り返すことで、天然由来原料の使用感を高める工夫を行い、「肌に良いもの・心地よいテクスチャー」の両立を追求しています。
具体的には、アルコールや防腐剤など刺激になりやすい成分を極力排除しつつ、保湿成分やベース成分の組み合わせで質感を調整。これにより、敏感肌の方にも使いやすいテクスチャーが実現されているのです。
そんなあなたにとって大切なのは、「成分単体の評価」ではなく、「全体としての肌への調和」であることを理解することです。
トレンド成分をどう活かす?季節性・社会背景の視点
現在注目されているのは、冷感成分や紫外線対策成分など、気候変動に対応した季節性アイテムです。たとえば、近年の猛暑を背景に、夏のスキンケア市場では「ひんやり感のある化粧水」が定番化しています。
ただし、こうした商品にありがちなのが「アルコール高配合による刺激問題」です。実際、取材企業では「アルコールの刺激を抑えつつ、保湿成分を加えることで心地よく使える処方」に改良した事例があります。
このように、トレンド成分を取り入れる際にも、「誰にとって心地よいのか?」という視点が欠かせません。
とはいえ、トレンドだけに振り回されると、本質的な商品価値を見失うリスクも。だからこそ、OEMのパートナー選びも慎重に行う必要があるのです。
原料選定の判断基準とOEMパートナーに求める視点
高品質な化粧品は、「どの原料を使うか」だけでなく、「どこから仕入れるか」も非常に重要です。
取材企業では、GMP(化粧品製造管理基準)に準拠した工場を採用し、安全性・安定性・エビデンスを兼ね備えた原料のみを使用しています。さらに、原料選定においては「開発力が高く、要望以上の提案ができる」工場との連携を重視。これにより、単なる受託製造にとどまらず、「開発パートナー」としての価値を提供できる体制を構築しています。
スキンケアOEMに取り組む際は、こうした「提案力」や「対応力」のあるパートナーかどうかを見極めることが、中長期的な成功の鍵となります。
成分表示にまつわる誤解と正しい理解
最後に、成分表示やその見方について、読者がよく誤解しがちな点を整理しておきましょう。
まず、「化粧品だけで劇的に肌質が変わる」と思い込んでいるケースが少なくありません。しかし、スキンケアはあくまで肌を整える補助的なものであり、生活習慣や体調も肌状態に大きく影響します。
また、「成分表示の順番が重要」「○○フリーなら安心」などの表記が、マーケティング的に過剰に扱われていることも。
取材企業では、「正しい洗顔」「毎日の保湿」「紫外線対策」の三本柱があってこそ、化粧品の効果が最大限に発揮されるとしています。
「成分を知ること=成分の名前を暗記すること」ではありません。成分がどんな役割を持ち、どう肌に作用するかを理解することが、本当の意味での成分選びなのです。
まとめ
この記事では、スキンケアの成分選びにおいて重要な視点として、以下の5点を解説しました。
・成分そのものよりも、テクスチャーと処方バランスが重要
・天然・ケミカルにこだわらず、安全性と使用感の両立を重視する
・季節性や市場背景に応じた処方設計が求められる
・GMP準拠や提案力のあるOEMパートナーが品質の土台となる
・成分表示やスキンケア効果への過信は禁物
「良い化粧品=良い成分」ではなく、「良い設計と継続ケア」があってこそ、肌にとって価値ある商品が生まれます。
OEMや自社製品開発を考えるあなたにとって、今回の知見が“納得できる製品作り”の一歩になれば幸いです。
【FAQ1】
Q:成分表示でよく見る「○○フリー」って、本当に安心できるの?
A:一概に安心とは限りません。刺激になりやすい成分を除いたという意味ですが、それだけで安全性が保証されるわけではなく、全体のバランスが重要です。
【FAQ2】
Q:天然成分だけでスキンケアを作るのは難しいですか?
A:天然成分中心でも開発は可能ですが、安定性や使用感のバランスを取るには工夫が必要です。信頼できるOEMパートナーと試作を重ねることで実現可能です。
【著者】
佐々木千草
【著者プロフィール】
職種:化粧品企画開発
経験年数:7年
化粧品業界にて7年間、スキンケア・メイクアップ・ヘアケア商品の企画開発に従事。市場・競合調査からコンセプト立案、容器・パッケージ資材の仕様選定及びデザイン立案、発注業務、販促支援まで一貫して担当。お客様目線と戦略的な視点を掛け合わせた商品づくりに努め、敏感肌・エイジングケア・機能性コスメなど幅広いカテゴリーに対応可能。
【監修】
小平 麻貴
【役職/専門領域】
商品開発部 部長
化粧品製造業・化粧品製造販売業 総括製造販売責任者